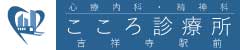休職・療養・復職
まずは休養、その後リハビリを徐々に行います。
うつ病などの治療で、いったん休職して、休養に専念する場合があります。
初期は休養に専念、改善してきたら、徐々にリハビリを行っていきます。
復職の際は、会社と相談しつつ、心理面も整理して、再発を防ぐことが大事です。
- 仕事に行けないなど、働きながらの治療が難しい場合、休職して療養に専念することがあります。
- 休職初期は休養に専念し、その後、徐々に段階的なリハビリを行っていきます。
- 復職には十分な活動量の他、「仕事への気持ちが整理できている」ことが重要になります。
- 事前に職場と復帰の形式、復帰場所について相談し、そこから逆算して準備を続けます。
- 休職時の生活のための制度(傷病手当・自立支援医療など)を適宜活用します。
- 集中的な、再燃予防も含めた休職中のリハビリとして「リワークプログラム」があります。
もくじ
はじめに
休職しながら治療することは少なくありません。
働きながら治療する方も多いですが、一方で病状によっては、休職してしっかりと療養に専念することが必要になることも少なくありません。
症状の改善や、その後の再発予防の双方にとって、休職しての治療は有効ですが、その間の生活や、復帰後などへの不安についてお聞きすることも少なくありません。
ここでは、休職および休職中の療養、復職の条件と段取り、休職中に活用できる制度やリハビリの枠組みなどを説明していきます。
- 症状によっては、休職して、休養に専念しながらの治療が必要なことがある。
- 休職から復職まで計画的に行うことが必要。活用できるサービス等も複数ある。
どんな時に休職するか
基本的には「働きながらでは改善が難しい時」です。
どんな時に、休職しながらの治療が必要になるでしょうか?基本的には「働きながらでは改善が難しい時」になります。具体的には、以下のような場合が想定されます。
①仕事にいけないとき
まず、仕事にいけない時が適応になります。仕事に行けない状態が続く時、会社としても「欠勤」が続き対応が難しくなり、ご本人としても毎日連絡が必要な中でなかなか「気持ちは休まらない」状態が続きます。
その解決策として、休職することで、ご本人は休養・治療に専念できるようになります。また会社としても対応の報告が明確になり、傷病手当金(後述)の制度も活用できるようになります。
②混乱など、職場で問題が生じているとき
会社には何とか行っていても、大きなミスを連発したり、混乱して周りに影響が出てしまう場合は、仕事の継続は困難です。
この場合も休職することで、ご本人の治療をしっかり行うとともに、職場での混乱等を続けないことで、職場内でのご本人の立場を守ることにつながります。
③働きながらの治療で改善しないとき
働きながらの治療を行っている場合、改善することも多いのですが、改善せずに不調が続く場合もしくは徐々に悪化が続く場合もあります。
この場合は、そのまま無理に「働きながらの治療」を続けても、症状が年単位で長期化してしまうことが想定されるため、いったん休職して療養・治療に専念した方が、結局近道になります。
休職期間は病状や状況等によって変わってきますが、一般的には「やや長め」に取ることが、余裕を持っての休養や再発予防のために望まれます。(例えば、うつ病の場合は3か月が目安です)
- 働きながらの治療が難しい場合は、いったん休職して療養・治療に専念する。
- 休職期間はやや長めの方が望ましい。うつ病の場合は3か月が目安になる。
休職の3つの目的
病状の回復・職場復帰・復帰後の再燃予防の3つです。
休職して療養に専念することで、どのようなことを目的にするでしょうか。まず病状の改善が重要ですが、その後の復職(もしくは転職)、復職後の再燃予防も同様に重要になってきます。
①病状の改善
まずは「働けない」ほどの精神的な不調を改善することが大事です。休職の初期は、この点に集中します。
休職して休養に専念することを土台として、必要時抗うつ薬を併用し、休養が難しい場合は、抗不安薬や睡眠薬などを併用して、休養の継続からの病状改善を図ります。
そして病状が一定の改善を見たら、まずは仕事に関係ないところから、段階的にリハビリを行い、「活動性」の改善を図ります。
②職場復帰
症状・活動性が改善するのも大事ですが、一番の目標は「職場に復帰する」ことです。
生活は大丈夫でも、「職場への葛藤」が強く仕事を考えると強い反応が出る場合は、すぐの復帰は難しいです。その場合は仕事への気持ちの整理を行っていき、それでも難しい場合は転職の可能性も検討します。
また、会社によって、復帰の枠組み(フルタイム等)や復帰場所(元の部署or異動)などのルールは大きく異なります。あらかじめ会社の制度をもとに復帰への話し合いをして、そこから逆算して、復帰の準備を続けていきます。
③復帰後の再燃予防
復帰も大事ですが、復帰後に「再燃しない」ことが、その後の長い仕事・人生にとって非常に重要です。
復帰後も「再発予防」の治療を続けていきながら、職場との相談や心理面の整理、ストレス・疲労対処の方法論の模索を継続し、再燃を防ぐ中での「仕事の充実」を図っていきます。
- 休職の目的は、「病状の回復」「職場復帰」「復帰後の再燃予防」の3つ。
休職の3つの段階
前期は休養に専念し、その後はリハビリを段階的に行います。
休職の療養では、初期(前期)はまず休養に専念し、その後段階的にリハビリをしていき、その後に復帰に向けての具体的な調整等を行っていきます。3つの段階に分けると、以下のようになります。
①前期(休養期)
休職を始めてすぐの時期です。この時期は症状が重く、まずはその改善のための休養が最優先です。
特に考え事を避けて「頭を休ませる」ことに専念し、ゆっくりすることで、徐々に症状が改善するのを待ちます。
多くの場合は抗うつ薬を症状改善のために使用し、また休養や睡眠が難しい時は抗不安薬や睡眠薬を併用します。
②中期(リハビリ期)
休養等で病状が改善してきても、疲れやすさ・動きにくさなどは残っています。中期では、その部分の改善を、段階的なリハビリにより図ります。
一気に動くと反動が来るため、まずは「仕事と無関係な運動」から、徐々に負荷を増やしながらリハビリしてきます。
5-7割ほど動けるようになったら、徐々に内容を仕事に近い内容にシフトしながら、慣らしていきます。
③後期(復帰準備期)
休養・リハビリで土台ができた中で、いよいよ具体的な復帰の準備を行い、復職につなげます。
リハビリとしては、図書館などで仕事に近いことを続けたり、通勤練習を行うなど、仕事に近いことを、仕事に近い強度で行うことで復帰の準備とします。
並行して、会社と復帰の相談を行っていきます。復帰の枠組み・場所を決めながら、復帰への段取りを決めて、実行していきます。
その際、準備していても、気持ちの「葛藤」から反応が強く出る事があります。その「葛藤」に徐々に慣らしつつも、職場への葛藤を徐々に整理していき、葛藤の影響の改善を図ります。もしそれでも葛藤が強いままの場合は、転職も選択肢になります。
- 休職は、前期(休養期)、中期(リハビリ期)、後期(復帰準備期)の3つに分けられる。
- 前期では、病状の改善のために、何よりも休養の継続を最優先にする。
- 中期では、活動性の改善のため、徐々に活動量を増やすリハビリを行う。
- 後期では仕事に近いことに慣らしつつ、実際に職場と話し合い、復帰に向けて準備する。
復職・再燃予防に必要なこと
活動量・心理面・ストレス対処の3つが必要です。
復職するための条件として「復職後のストレスがかかっても再燃のおそれが十分に少ない」ことが求められます。そのために必要なことをまとめると、次の3つになります。
①日中十分活動できること
多くの会社では、復帰後「フルタイム(1日8時間)週5日」での勤務になります。通勤も含めて、フルタイムで動けるだけの活動量があり、かつ土台としての生活リズムの安定があることが、復職のために必要になります。(なお、時間短縮での復帰が可能な場合、必要な活動量はやや下がります)
②仕事への葛藤が表面化しないこと
復職することは、多くの場合、「休職前に感じていた葛藤」に再度さらされることを意味します。それでも再燃しないことが求められるため、心理面の整理をするなどして、その葛藤に十分対処でき、表面化しない状態になっていることが必要になります。(なお、前の部署にのみ葛藤が強い場合は、異動しての復職も選択肢になります)
③ストレス・疲労への対処技術があること
復職後は、休職前と同様に、日々ストレス・疲労がかかる状態になります。その中で再燃を防ぐために、十分なストレス・疲労への対処技術を獲得していることが求められます。
- 復職の条件として「仕事のストレスが再度かかっても再燃しない」状態が求められる。
- 具体的には「十分な活動量」「仕事への気持ちの整理」「ストレス対処技術」が求められる。
復職への相談と段取り
多くの場合、復帰前に「産業医面談」があります。
復職に向けて、会社と相談し、段取りを決めていく必要があります。これは会社ごとにかなりルールが異なるため、個別に調整していく必要がありますが、大まかには、次の3段階がベースになります。
①会社との事前相談
休職中期の終わりごろを目安に、会社と、復帰に向けての事前の相談を始めていきます。その中で、復帰の形式(フルタイムor短縮)、復帰場所(もとのところor異動)、復帰への段取りにつき聞いておき、その後に備えます。
②主治医から復帰可能の診断書をもらう
復帰形式・復帰場所をもとにリハビリを継続し、主治医に復帰可能かを尋ねます。大丈夫であれば、主治医から「復職可能」の診断書をもらいます。(これを、産業医面談の際に出します)
③産業医面談等
復帰前に職場にて、産業医面談もしくはそれに代わる面談(人事面談等)を受けます。ここで今の状態や活動状況などを伝え、復帰可能か、産業医等の判断を仰ぎます。復帰可能との判断になれば、その後数日して復職になります。
- まず、復帰の少し前に、会社と事前面談し、復帰の形式・場所・段取りの確認をしておきます。
- そのうえでリハビリ後主治医から復職可能の診断書をもらい、産業医面談を経て復職します。
休職時に活用する制度
傷病手当制度など、活用できる制度があります。
休職時には、生活のことが心配になり、ゆっくり休めないとの声も聞きます。
実際には、ここで紹介する「傷病手当金」の制度などを活用することで、だいぶ不安材料をカバーできます。制度は十分に活用しつつ、しっかりと療養に専念し、回復・復職につなげていただけると幸いです。
代表的な制度として、次の2つがあります。
①傷病手当金制度
「けがや病気で休職する場合に、給与の一部を支給する手当金」の制度です。休職後、申請書を継続して提出することで、休職中最大1年半、給与の約2/3が支給される制度です。
申請書にはご自身、会社、主治医が書く書類がそれぞれあり、その中で主治医分は、医療機関に依頼して書いてもらうことになります。
②自立支援医療
うつ病等のこころの不調で継続しての通院が必要な場合、申請すると、3割の医療費が1割になる制度です。市役所に申請しますが、その場合に、かかっている医療機関の診断書(特定の書式あり)が必要になります。受診中の方は、主治医にご相談ください。
- 「傷病手当金」は、休職中、給与の約2/3が支給される制度。最大1年半が期限。
- 「自立支援医療」は、医療費が3割→1割になる制度。診断書を主治医が記載し、市に申請する。
集中的なリハビリ「リワーク」
休職中にグループで、集中的にリハビリする方法です。
ここまで、休職の各時期での療養方法、および復職に必要な要素などを見てきました。
これらの取り組みは、もちろん自分で行う方法もありますが、本調子でない中一人ではなかなか全部は行いにくく、特にストレス対処法獲得などは、独学では難しい面も少なくありません。
これらの「活動の強化」「心理面の整理」「ストレス対処法の獲得」を包括的、集中的にグループで行っていく方法が、「リワーク」です。
「リワーク」では、初めは週2-3回、最終的には週5回(1日約6時間)継続して通い、復職に向けた様々なプログラムを、グループで集中的に受けていきます。これにより、期間は2-4か月かかりますが、復帰に向けての準備をまとめて行っていくことができます。
特に、リハビリや復帰準備が、自分だけではなかなかスムーズにいきにくい場合や、何としても再燃を防ぐベストを尽くしたい場合などは、大いに選択肢になると思われます。(なお、当法人では、本院(府中)にて、リワークを行っています)
- リハビリ、心理面の整理、ストレス技術の獲得をすべて独力で行うのは困難も大きい。
- その一つの解決策として、グループで集中的にリハビリする「リワーク」がある。
まとめ
こころの治療において、いったん休職して療養に専念し、その後復職をすることがあります。
初期は休養に専念し、その後リハビリ→復職準備と進んでいきます。復職は「その後再燃しないこと」が大事なため、十分な活動・気持ちの整理・ストレス対処法の獲得の3つをしたうえで、会社とも相談し復職していきます。
休職中に行う取り組みは実はかなり多く、しっかり復職後の安定につなげるため、集中的なリハビリである「リワーク」を活用することも、一つの選択肢になります。
- こころの治療において、いったん休職して療養に専念し、その後復職することがある。
- 初期は休養に専念し、その後リハビリ→復職準備と段階的に進めていく。
- 一人では取り組みが難しい場合などは、集中的なリハビリ「リワーク」の活用も一案。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)