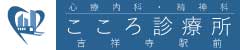認知症
ゆっくりと進んでいく「物忘れ」
物忘れがゆっくりと進みつつ、不安などの「周辺症状」も出る事があります。
対策しやすい「周辺症状」の対処がカギ。早期での治療開始が望まれます。
治療と介護サービスの活用を並行、生活・人生の改善を図ります。
- 認知症は、徐々に進む物忘れなど、少しづつ「脳の機能」がうまくいかなくなる不調です。
- 物忘れなどの「中核症状」のほか、不安・イライラ等の「周辺症状」も出る事があります。
- 他の原因が隠れていることもあり、質問・検査などを合わせて、慎重に診断します。
- 「中核症状」には、「進行を遅らせる」薬を使いますが、進行自体は止まりません。
- 「周辺症状」には薬を使うこともありますが、環境を整えることも有効とされます。
- 環境を整えるために「介護保険」を用いた「介護サービス」活用が時に有効です。
もくじ
はじめに
治療と介護サービスを合わせての、早期からの対処が重要です。
ご高齢の方に、徐々に「物忘れ」が進むほか、生活や考えることなどが徐々に苦手になる脳の不調、それが「認知症」です。
治療・対応がない状態で症状が進むと、周囲とトラブルになったり、精神的にも混乱し、対応が難しくなる場合があります。
一方で、早めに治療・対処をすることで、特に精神的な不調である「周辺症状」の予防・改善を図ることができ、認知症があっても、その人らしい生活を目指しやすくなります。
ここでは、認知症について、症状や治療・対応法などを見ていきます。
- 認知症とは、「物忘れ」など、徐々に考えることや生活の活動が苦手になる脳の不調。
- 治療・対応ないまま症状進むと、環境・精神面が混乱し、対応が難しくなることがある。
- 診断・治療と介護サービスを早めに行うことで、生活面などの悪化予防などが期待できる。
認知症の原因
脳の機能の低下が原因ですが、詳細は多くが不明です。
認知症は、基本的には「全般的な脳の機能の低下」が原因となります。一方、それがなぜかは、まだ解明されていない部分が多いです。
代表的な認知症である「アルツハイマー型認知症」では、「アミロイドタンパク」と言われる物質の影響などが言われ、研究が進んでいますが、まだ不明な点も多く、研究に沿った薬の実現も、まだ途中の状態です。
ただし、中には、アルツハイマー型ではない「原因がはっきりした」認知症の場合もあり、対応が変わるため、それは診察・検査の中で見分けていくことになります。
- 認知症は「全般的な脳機能の低下」だが、その原因は、まだ研究中で、不明な点が多い。
- ただし、一部原因のはっきりした「対応できる認知症」があり、診察等で見分けていく。
認知症の症状
脳の不調(中核症状)とこころの不調(周辺症状)の2つです。
認知症の症状は、大まかにいうと、脳の不調(中核症状)とこころの症状(周辺症状)の2つに分けられます。
このなかで、特に介入が重要なのが、こころの不調(周辺症状)です。この周辺症状が強くなると周囲とのトラブルや事故の危険などが生じる一方で、介入により予防・改善が見込める部分が大きいためです。
では、この2つの症状を、もう少し詳しくみていきます。
①脳の不調(中核症状)
「脳の機能の低下」から、直接出てくる症状です。記憶力の低下(物忘れ)のほか、時間や場所の感覚(見当識障害)、考えたり、感じ・実行する力の低下(認知機能障害)など、幅広い範囲で症状が出てくることがあります。
例えば、次のような症状が出ます。
物忘れの症状
- 同じ話をくり返す
- 鍵や財布など、大事なものをなくす
- 同じものを何度も買ってくる
- すぐ前に話した電話の相手の名前を忘れる
- 最近知り合った人の名前をすぐ忘れる
ほかの中核症状
- 道に迷ってしまう
- 会話についていけなくなる
- 時間を忘れる、間違える
- 小銭を計算できず、すべて札で払う
- 料理の味付けが変わってくる
これは、脳の機能の低下での症状のため、徐々に進んでいくことが特徴です。
②こころの不調(周辺症状)
脳の「中核症状」があると、「前できたことがうまくいかない」「なぜか怒られてしまう」など、ストレスがかかることが多くなります。
その結果、ストレスと、脳機能の「ストレスへの余裕のなさ」を背景とした「こころの不調(周辺症状)」が出てくることがあります。
症状は様々な分野に出てくることがあり、重さもそれぞれです。例えば、次のような症状が出ます。
周辺症状(軽め)
- 意欲がなくなる
- いろいろなことが不安になる
- ものを集めてしまう(収集癖)
- イライラしやすい(易刺激性)
- 生活リズムの乱れ
周辺症状(重い)
- 外を歩き回る(徘徊)
- 興奮・大声・暴力
- 幻覚・ものとられ妄想
- 食べられないものを食べる(異食)
- 服を脱ぐ・性的逸脱行為
特に重い周辺症状が出ると、ご本人の尊厳がそこなわれるほか、周囲とのトラブルになったり、生活を続けること自体が難しくなることがあります。
一方で中核症状と比べると、心理面・環境面の働きかけによって、改善を見込みやすい症状でもあります。
早い段階での治療・ケアをお勧めする最大の理由は、この「周辺症状の予防・改善」にあります。
- 認知症のおもな症状は、脳の症状(中核症状)と、こころの症状(周辺症状)の2つ。
- 中核症状は物忘れのほか、考え・感覚など広範囲であり、徐々に進行していく。
- 周辺症状はストレスも影響し、変動しつつ、人によっては重い症状も出る。
- 周辺症状対策が認知症対策のカギ。そのため、早い段階での治療開始が望まれる。
認知症と似た病気
うつ病や体の病気で、認知症と似た症状が時に出ます。
たとえば「うつ病」など、一見、認知症と似た症状を起こす「別の病気」があり、それが原因のことがあります。もしそれがあれば、その対策を取ることで改善するため、診察の中で見分けていくことが大事です。
以下に、代表的な「別の病気」の例と特徴をまとめます。
「別の病気」の例
- 正常な老化
- 脳血管性認知症
- びまん性レビー小体病
- 脳や体の別の病気
- 老年期うつ病
正常な老化
- 特に80歳以上になってくると、認知症がなくても、徐々に「脳の機能の低下」が起こってくる。
- 進むスピードが認知症より遅く、「周辺症状」は出にくい。
- 経過・画像検査などで見極めるが、判断が難しい場合も少なくない。
- ただし、判断が難しい場合は、おおむね生活への支障は限られる。
脳血管性認知症
- 動脈硬化・高血圧や、「小さい脳梗塞」などが原因で生じる認知症。
- 特に高齢では、アルツハイマー型との合併の場合が多い。
- イライラ・大声などの症状が多くなる傾向がある。
- 血圧の治療など、もとの「脳血管」への治療を行っていく。
びまん性レビー小体病
- パーキンソン病と原因が似たタイプでの認知症。
- 症状として、物忘れの他「小刻み歩行」「幻が見える(幻視)」が特徴。
- 症状・経過と、特殊な精密検査などを合わせて、診断を確定する。
- 「薬の副作用が出やすい」ため、見分けることが重要。
脳や体の別の病気
- 以下のような、脳や体の病気で「認知症の症状」出る事あり、見つかれば治療で改善しやすい。
- 慢性硬膜下血種→転んだあとの慢性的な「脳出血」。画像検査でわかる。
- 正常圧水頭症→脳の空洞(脳室)が広くなる。画像検査でわかる。
- 甲状腺機能低下症→うつ症状のほか、物忘れ類似の症状も出る。採血でわかる。
老年期うつ病
- うつ病でも、「記憶力の低下」「意欲低下」など似た症状が出て、時に見分けにくい。
- 認知症と比べ、「自覚症状が強い」ことや、落ち込み・不安が強いことが特徴。
- 認知症と比べると、進行が早く見えることが多い。
- 「うつ病」の治療をすることで、改善することが見込まれる。
- 「別の病気」が原因で、認知症と似た症状が出る場合がある。
- その場合はその病気の治療で改善するため、診察で見極めることが重要。
認知症の診断について
症状の経過、質問の検査、画像等の検査の3つを合わせます。
認知症の診断では、主に「認知症であるか」「別の病気が隠れていないか」の2つに関して見ていきます。具体的には、これまでの症状の経過(病歴)を聞くことを主に、今の症状(質問の検査)、画像などの精密検査を組み合わせて、確定診断を行います。
具体的には、以下のようなことをします。
症状の経過
- どんな症状が、いつから現れ、どう変化したかを聞く。
- 中核症状、周辺症状の双方について聞いていく。
- 生活状況や、日常生活の状況もあわせて聞く。
質問の検査
- 診察時、どのような症状があるかを、質問の検査を使ってみていく。
- 主に、30点満点の「長谷川式検査」を用いる。
- 点数のほか、間違う場所や答え方の様子も合わせてみていく。
画像等の検査
- 血液検査→甲状腺など、体の原因がないことを確認
- CT検査→脳の別の原因がないことを確認
- MRI検査→脳の状態を、より精密に見る
- SPECT、PETなど→大学などで、精密に見るときに行う
- 認知症の診断は「認知症があるか」「他の原因が隠れてないか」を中心に行う。
- 具体的には、「症状の経過」「質問の検査」「画像検査等」を組み合わせて行う。
認知症の治療・対応の3つの柱
中核症状対策・周辺症状対策・ケア導入の3つです。
認知症では、中核症状と周辺症状の2つの方法があり、また、医学的治療のほかに、介護保険制度を用いたケアの活用が重要になります。
主に行う内容をまとめると下のようになります、詳細は、次の章以降になります。
中核症状対策
- ドネペジル等、「認知症の進行を遅らせる」薬を用いる。
- 日ごろから「頭を使う」ことを意識して、進行を遅らせる。
- 自分だけで難しい時は、デイサービスなどを検討する。
周辺症状対策
- まずは、生活・環境を整えて、ストレスを減らしていく。
- そのために、デイサービス等の介護サービスも必要に応じ活用する。
- それでも難しい場合に、必要最低限の薬を検討する。
ケア導入
- 介護保険を受けるには、「かかりつけ医」がいることが必要。
- まず診察・診断を受け、そのうえで市役所に相談・導入する。
- 「ケアマネージャー」と協力して、ケアを計画、導入する。
- 認知症の治療の柱は「中核症状対策」「周辺症状対策」「ケア導入」の3つ。
- 医学的治療のほか、介護保険制度を用いた「ケア体制の確立」が重要。
治療①中核症状への治療
「進行を遅らせる薬」を使いつつ、頭を使う習慣を。
中核症状には、ドネペジル等の「進行を遅らせる薬」を使います。ただし、これはあくまでも「進行を遅らせる」作用であり、「進行しない」もしくは「改善する」ものではありません。そのため、できる対策として「進行を遅らせる」ことはしつつも、「徐々に進行する」ことを受け入れつつ、対策を取っていく必要があります。
また、生活の面では、「頭を使う」習慣が重要です。体を普段から使うことで「体の機能を保つ」ことと同様に、頭を普段から使うことで「脳の機能を保つ」ことが、「進行を遅らせる」点からは、やはり有効です。
「頭を使う習慣」は、自主的に取り組むことでも有効ですが、特に「無気力・意欲の低下」などがある場合は、なかなか自分では難しいこともあります。その場合は、デイサービスなどを導入し、サポートの枠組みの中で「頭を使う習慣」を保つのも有効と思われます。
- 中核症状には、ドネペジル等の「進行を遅らせる薬」を使って、進行を遅らせる。
- 生活では「頭を使う習慣」が重要。自分で難しければ、デイサービス等を活用する。
- いずれも「進行を遅らせる」目的で、進行はするため、受け入れつつ対策を。
治療②周辺症状への治療
まずはケア導入も含めた環境調整。それでも難しい時に薬を検討。
周辺症状は、多くの場合、症状の悪化に、「生活・環境でのストレス」がからんでいます。まずは、その点での改善を図ります。
「わかりにくい」「落ち着かない」「役割がない」ことがストレスの大きな要因です。環境調整として、まずは細かい「余分な刺激」を減らしてなるべく家をシンプルにして落ち着きを図ること、および大きく、わかりやすく場所の説明の紙を張るなどとしてご本人の負担を減らし「わかりやすくする」ことが有効です。そして可能なら、家での「役割・長所」を見つけ、できたことをほめることで、「役割・自己肯定感」を保ってもらうといいでしょう。
これらは家だけでは難しかったり、長時間だと介護する側の人が疲れ切ってしまうことがあります。そのため、デイサービスを主体とした介護サービスを導入し、枠組みとして「わかりやすく・落ち着けて・役割がある」状況を作るのが、ご本人・介護者の双方にとって有効と思われます。
こうした環境の調整だけでは周辺症状が治まらなかったり、強い周辺症状のために生活が難しい場合は、くすりの使用を検討します。
年齢もあり、薬による負担もあるためなるべく最小にとどめたいですが、「使わないと生活・介護が困難」であれば、必要最小限で使っていきます。その場合抗精神病薬・抗うつ薬などを用いますが、「抑肝散」などの漢方薬が、安全には使いやすいと思われます。
それでも症状が強く、生活を続けることが難しい場合は、一旦入院して立て直すことが必要になる事があります。しかし可能なら、なるべく入院に至る前に、対策を取り、改善を図りたいところです。
- 周辺症状には、まずは「わかりやすく・落ち着けて・役割がある」環境づくりを。
- そのために、必要に応じて、デイサービス等の介護サービスを活用していく。
- 環境調整のみでは難しい場合、健康に注意しつつ、最小限の「くすり」を使う。
治療③ケア導入
薬の治療と並び、介護サービスの活用が重要です。
中核症状や、強い周辺症状には薬の治療を行っていきますが、それと並んで、生活面を支えるための「介護サービス」の活用が、認知症の対策に重要です。
介護サービスの活用には、「介護保険」の認定を受ける必要がありますが、そのためには、医師に「診断」を受ける必要があります。
医師に(認知症の)診断を受けたうえで、市の「介護保険窓口」に申請を行うと、調査を経て、要介護度が決まり、介護保険の利用が可能になります。
その後、近くの「ケアマネージャー」に相談し、使うサービスを決めた「ケアプラン」を作り、実際にサービス利用になります。
サービスの種類は多いですが、メインは、週数回定期的に通う「デイサービス」と、短期間宿泊する「ショートステイ」の2つです。ご本人が活動して周辺症状の予防等を図るほか、介護するご家族が心理的余裕を持ち、無理なく介護を継続するための助けにもなります。
経過により症状が変化するため、それに合わせてデイサービスの頻度の見直しなど、ケア体制の調整を行っていきます。
- 認知症ケアには、薬などの治療の他、介護制度を用いた介護サービス活用が大事。
- 診察、診断を受けたうえで市に相談、調査、ケアプランを経てサービスが利用できる。
- サービスの種類は多いが、日中通う「デイサービス」と短期宿泊の「ショートステイ」が大事。
まとめ
早くから治療・ケアを行い、周辺症状の予防を目指します。
認知症は、特に重い「周辺症状」が出ると、生活に大きな困難が出てしまいます。一方、早期から治療とケアを始めていくことで、周辺症状を予防し、物忘れ自体は徐々に進んでも、生活は崩さず、その人らしい人生を継続していくことが期待されます。
治療をするにも、介護保険を受けるにも、まずは診察と診断が必要になります。もし物忘れの兆候があれば、早めのご相談をお勧めいたします。
- 認知症は、特に「周辺症状」が重くなると、本人・周囲の生活に大きな困難が出てしまう。
- 一方で、早期からの対策で、特に「周辺症状」は悪化を防ぎやすい。
- 治療・介護制度の双方のために診察・診断が必要。症状があれば早めにご相談を。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)