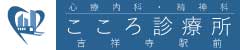ASDのタイプ3+2
タイプで影響・対策変わる
ASD(自閉症スペクトラム)には、基本3つ+特殊2つの計5タイプあります。
タイプにより症状の出方や影響、対策の方法が変わってきます。
もくじ
(1)はじめに:ASDのタイプ3+2
ASDセルフチェック。今回は「ASDのタイプ3+2」についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
ASD(自閉症スペクトラム)は、「こだわり」と「対人面の困難」が目立つ発達障害です。
一方で人によってタイプがいろいろ違うことがあり、どのタイプのASDの人と接するかで、印象も変わってくるところがあります。
今回は「ASDのタイプ3+2」について見ていきたいと思います。
(2)ASDにも色々なタイプがある
「ASDのタイプによって影響も対策も変わってくる」のがポイントです。
<ASD(自閉症スペクトラム)とは>
ASDは「社会性の障害」と「こだわり」の2つが目立つ生まれながらの発達障害です。
幼少期にわかることも多いですが、10代から成人になってから見つかることもあります。
同じASDでも出方のタイプが大きく異なることがあります。
例えば「強引に周りを巻き込むタイプ」の方もいますし、「誰にも関わらず孤立するタイプ」の方もいます
タイプによって、その影響もその対策も大きく変わってくるところがあります。
(3)ASDの3つのタイプ
ASDは、そのタイプによって大きく違って見えてきます。
主には「積極奇異型」「受動型」「孤立型」の3つに分類されます。
①積極奇異型
「人に働きかけるんだけれども、浮いてしまう」というタイプです。
<積極奇異型とは>
積極奇異型は「自分のルールで積極的に他者に働きかけていく」というタイプです。
一方で、「一方的になってしまう」ことが多く、「こだわりを押し付けてしまう」ことがよく見られます。
そのため「行動力」はある一方で、他者とのトラブルも多くなってきます。
②受動型
「一見、おとなしく気づかれにくい」というのが特徴です。
<受動型とは>
受動型は、受け身の状態を背景にある種「自分が不明確」になり、流されやすいタイプです。
一見、奇妙さは少なくて目立ちにくく、トラブルも少ないです。
一方、相手に利用されたり、支配・搾取される危険も強いため、注意が必要です。
③孤立型
「自分の世界の内側で生きる」タイプです。
<孤立型とは>
孤立型は、ま「るで他人がいないかのように」自分の世界だけで生きるというタイプです。
好みや服装などの独特さが、このタイプの方は目立つことが多いです。
そして、雑談が特に苦手というところがあり、基本的には一人での生活を好みます。
<3つのタイプの傾向>
まず「積極奇異型」は男性に多く、「人間関係のトラブル」などで見つかることが多いです。
「受動型」は逆に女性に逆に多く、10代での同年代との「不適応」や「うつ」などからよく判明します。
「孤立型」は男女とも症状が重めの方が多く、集団検診などでの「明らかな奇妙さ」でよく判明します。
(4)ASDの特殊なタイプ2つ
先ほどの3タイプのような「典型的」ではない場合があります。
この「ASDの特殊なタイプ」は「尊大型」「大仰型」の2つです。
④尊大型
これは「他者を見下すタイプのASD」です。
<尊大型とは>
尊大型は、こだわりを強く押し付けたり、相手を見下すことが非常に目立つタイプです。
これは純粋なASDというよりも、ASDがもとにあって、そこにいわゆる「自己愛性パーソナリティ障害」が「重ね着」した状態です。
このタイプですと、非常にトラブルが多く、対策が難しいのが現状です。
⑤大仰型
「丁寧に振る舞うが、不自然さが残る」というタイプです。
<大仰型とは>
大仰型は、元来別のタイプだったのが「意図的に適応を図る」結果、様々な相手に対し丁寧になります。
しかし、一方で、とっさの時にはどうしても一部不自然な部分が残ってしまうことがあります。
そして、一種の「過剰適応」の面があり、ストレスやうつ等の精神不調になることもあります。
(5)ASDの各タイプの対策
共通点は「特性を受け入れつつできる取り組みをしていく」ことです。
①積極奇異型への対策
まずは場に応じて「黙る」スキルを身に付けることです。
「空気を読まず色々言ってしまう」ことを是正するために、一歩引けることが一番大事なスキルです。
その上で、他者の会話などのパターンを観察し、「話す」「黙る」タイミングを徐々につかむことが大事です。
それによって相手から「一方的に奪う」交流パターンを脱することが大事です。
②受動型への対策
一番大事なスキルは「嫌なことがあった時にしっかり断る」スキル。
これはトラブルなどを避けるために、まず一番大事なスキルになります。
その上で無理せず、自然に交流できる友人を「少なくてもいいので」探していき、安定を図ることが大事です。
その中で、「自分の軸」について試行錯誤を経つつ徐々に探していくことが大事です。
③孤立型への対策
まず大事なのが「最低限の交流スキルを身に付ける」こと。
仮に「一人で生活する」といっても最低限の交流は必要になるため、そこをまずクリアします。
その上で「自分のこだわり」と「社会のニーズ」の接点を探していきます。
見つかった場合は、「社会のプラスになること」に「こだわる」ことを通じ、それを通じ社会適応を図ります。
④尊大型への対策
この対策は難しいところがあります。
可能であれば、「自分の行動」人を見下すなどの行動の自他への影響をしっかり見ていくことが大事です。
そのうえで社会適応のルールとしての「信頼残高」の話に立ち返り、行動の調整を図りたいところです。
但し、現実には難しさもあります。
「周りとしてはどうするか」、孤立すると標的になるため孤立せず、「チームとして」冷静に対応していくことが大事です。
そして可能なら「組織ルールの整備」他者から「奪う事」は容認できないことを、本人の人格否定はしない形で明示したいところです。
⑤大仰型への対策
まずは直面・努力してきた自分をしっかり「認める」こと。
他者からの評価は時に微妙な場合もありますが、努力自体は確かなので、その自分をしっかり認めることが大事です。
その上で「スキル」の精度の改善を、絶え間なくやっていくことが大事です。
そして、どうしてもストレスがたまることが課題のため、「ストレスマネジメント」の徹底が大事です。
これらを経た上で、最終的に「自分の強み」をしっかり生かすことが大事になります。
(6)まとめ
今回は、ASDセルフチェック「ASDのタイプ3+2」について見てきました。
ASD(自閉症スペクトラム)は特殊なものを含めると以下の5タイプがあります。
●自分ルールで動きすぎる「積極奇異型」
●受け身で流されやすい「受動型」
●他者との交流を欠いてしまう「孤立型」
●他者を見下してしまう「尊大型」
●適応への途中経過としての「大仰型」
タイプごとにそれぞれ困難がある一方対策もあるため、タイプを見極めた上で、日々の改善の取り組みを続けることが大事です。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)