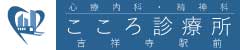女性のASDの特徴5つ
女性特有の特徴もある
女性のASDでは、「ASD全般の特徴」と「女性ASD特有の特徴」の双方あります。
後者は「受動型」「過剰適応」等で、10代以降の発見が多くなります。
もくじ
(1)はじめに
女性の発達障害。今回は「女性のASDの特徴5つ」についてやってきたいと思います。よろしくお願いします。
女性の発達障害の中でADHDと比べると頻度が少ないとされる「ASD」。
一方、臨床の場面ではグレーゾーンの方も含めると少なくない方からのご相談を受けることがあります。
今回は、「女性のASDの特徴5つ」について見ていきたいと思います。
(2)ASDの特徴と女性での特徴
「ASD特性は共通のものもあれば、女性では一部違うものもある」のがポイントです。
<女性のASDの2要素>
「女性のASD」には2つの要素があります。
まず「ASDの要素」。これは男女共通のこだわり等の要素です。
もう1つが「女性のASD特有の要素」、一部男性との違いがあります。
<ASDの代表的な症状2つ>
①社会性の障害
相手の表情や雰囲気など「非言語的な要素」を受け取ることが困難なことが要点です。
②こだわり
「一つの細かいことにこだわる」。言い換えると「急な変化や予測困難に弱い」特性です。
<男女共通のASDの代表的な症状>
まずは「対人面の交流が困難」なこと。
そして「急な変化があった時にこだわりの関係で困難が出る」こと。
もう一つが「感情表現が乏しい」ことです。
<女性のASDの特徴>
まずタイプは「受動型」、受け身で流されやすいタイプが多いのが特徴です。
そのため一見目立ちにくい一方で、「人に流されてしまいやすい」ことが特徴です。
その結果発見がしばしば10代以降と遅くなった結果「二次障害」が出やすい面があります。
<女性ASD早期発見の必要性>
女性ASDの方はなかなか目立ちにくいため見つかりにくいです。
一方で、発見が遅れれば遅れるほど、「うつ」など二次障害が悪化しやすい面があります。
なので早い段階での発見や対策が望まれるところです。
<診断後の対策>
1つ目は自主的な対策。例えばグレーゾーンでも傾向がわかれば、改善のスキル獲得等の取組みが可能です。
若年の方なら「療育」をすることがあります。サポートを通じ特性改善や二次障害予防を図ります。
成人で仕事が困難なら「就労移行支援」。自主的な対策だけでは困難な時に利用が検討されます。
(3)女性のASDの特徴5つ
「ASDの特徴と女性ASD特有の特徴」の双方があります。
①雑談が苦手
「ASDでは雑談は非常に苦手」です。
<雑談とは>
雑談はテーマを決めずに行う一種の世間話になります。
何かの達成目標はなく、交流自体が一種の目標になってきます。
その中で、特有の理由がない中で「話題が移り変わる」ことが目立ちます。
ASDでは、この「雑談」が非常に苦手です。
<ASDでの雑談が苦手な点>
まずは「雰囲気を読む」非言語的な面を読むことは、社会性の障害で非常に苦手です。
そして、「内容が曖昧である」ことに理解等の難しさがあります。
そして、「話題が急に変化する」急な変化への対応が苦手です。
<雑談が重要な場面>
一つは、思春期のいわゆる同年代のいわゆる「ガールズトーク」と言われるもの。
そして「職場」で対人関係が重要な職場の場合、適応のために重要になります。
あとは「個人的な人間関係」、「恋愛」「結婚」、出産後の「ママ友」等があります。
これらが苦手ですが、逆に苦手の発見が「ASDに気づくヒント」にもなる部分があります。
②マルチタスクが苦手
「同時並行がASDでは苦手」です。
<マルチタスクとは>
マルチタスクは、同時並行で複数のことをやっていくことになります。
これは子供の頃と比べて、大人・社会人になってから非常に増加してきます。
そして、近年はAIの普及等から、仕事等でもマルチタスクが求められることが増えています。
<マルチタスクが大事な場面>
まずは「仕事」業種次第ですが、特に最近はしばしばマルチタスクが求められます。
また「家事」家のことは複数同時にやっていく必要が出てきます。
「育児」子育てはマルチタスクおよび臨機応変が必要、かつ家事と並行する必要があります。
<女性ならではのつらさ>
まず女性だと、世間的に男性よりマルチタスク的なことが求められやすい面があります。
そして同性だとマルチタスクが得意な方が多く、比べられやすい面があります。
そして、「結婚後に」マルチタスクを求められることが増え、そこで弱点が強く出やすいです。
③表情が動きにくい
ここには「社会性の部分とこだわりの双方」が影響します。
<表情等の乏しさ>
ASDでは感情を出す「表出」が乏しくなりやすい面があります。
その中で「表情」や「声のトーン」などが乏しくなりやすいです。
この結果場合によっては、「無愛想」など否定的な評価につながることもあります。
<乏しくなることの例>
まずは「顔の表情」ろが乏しくなることがあります。
あとは「声の抑揚、トーン」も乏しくなることがあります。
また「体の動き」が乏しく、あまり動かない場合があります。
<対策1:意図的に強める>
表情など「乏しい」と言われているのであれば、「意識的に」表現を強めカバーするのが一案です。
表現が得意な他者をモデリングして練習し、習得していきます。
これで乏しさの改善は見込めますが、どうしても一部不自然さが残るのが弱点です。
<対策2:自分のスタイルを確立する>
どうしても「乏しさは欠損」と考えると、劣等感や低評価につながりやすくなります。
逆にある種「個性」と風に割り切り、、それに合わせた自己演出をしていきます。
ただ、その中で「他者を不快にさせない方向性」で演出することが必要になります。
④流されやすい
「良くも悪くも相手に影響される」というところです。
<女性に多い「受動型ASD」>
女性に多い「受動型ASD」は、受け身で自己表現が少なく、周りに合わせるタイプのASDです。
なので一見奇妙さだったり、トラブルというところは少なく、外からは目立ちにくいです。
一方で「悪意ある他者に利用される」、及び無理をして「二次障害」が出やすいことに注意が必要です。
<「流されやすい」の背景>
まず「過剰適応」する傾向があり、結果自分の「軸」が不明確になり流されやすくなります。
また「感情などの言語化の苦手さ」が「脳の特性で」あり、そのため「自己主張がしにくい」面があります。
結果「流される方が」波風立たずうまく行きやすいという「人生経験」につながり、それも影響します。
<流されやすい時の影響>
まずは「損な役回り」を押し付けられやすい面。
また、本心とのずれが出た時「ストレスが増えて二次障害が出やすい」面。
あとは相手に悪意があった場合支配されたり、利用されてしまいやすいリスクがあります。
<「流されやすい」の対策>
まず大事なのは「理不尽なら断る」スキルの獲得です。
その上で余裕があれば「自分軸」自分が何をしたいかを模索していきます、
そして「表現の練習」を意識的にやっていくことが大事です。
⑤二次障害が出やすい
「我慢が重なって二次障害に」至るリスクがあります。
<発達障害の二次障害>
二次障害は、「不適応や過剰適応」等のストレスから二次的に起こる症状です。
「うつ」など内側に向く場合と「イライラ」など外側に向く場合があります。
これは非常に社会生活に影響が強い一方、環境や技術などで変化の余地があり、対策が非常に重要です。
<女性ASDでの「過剰適応」>
女性のASDでは無理に合わせる「過剰適応」が多いです。
過剰適応によりトラブル自体は減り外からは目立ちにくくなります。
一方でストレスが強まり、目立たないため発見が遅れる事もあり、「二次障害」が出やすくなります。
<女性での二次障害>
女性の二次障害は「過剰適応」を背景に出やすい面があります。
そして、「うつ」や「体の症状」など内側の症状で出ることが多いです。
そのため気付かれにくく、逆に発見が遅れ慢性化・重症化しやすいのがリスクです。
<女性の二次障害の例>
まずは「うつ」や「不安」の症状で出やすいです。
また、頭痛や朝起きづらいなど「体の症状」で出やすいです。
また人により「摂食障害」拒食や過食で出やすい方もいます。
<二次障害への対策>
様々な角度からストレスを何とか減らすことが対策です。
まずは「環境調整」を可能であれば行っていきます。
また、色々なスキル獲得も含めての「ストレスマネジメント」。
もう一つ大事なのが「早目に診断をして早めに対策を取る」ことです。
(4)まとめ
今回、女性の発達障害「女性のASDの特徴5つ」を見てきました。
女性のASDでは、「ASDの特徴」と「女性ASD特有の特徴」の2つがあり、以下の5つが代表的です。
- ●雑談が苦手
- ●マルチタスクが苦手
- ●表情が動きにくい
- ●周りに流されやすい
- ●二次障害が出やすい
これらが苦手ですが、「苦手は気づくヒント」という面もあります。
早期診断は二次障害の改善に大事ですので、今回の5つがもしあれば可能性を検討してみてください。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)