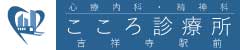バルプロ酸(デパケン)
特に躁の改善見込む「気分安定薬」
バルプロ酸(デパケン)は、躁うつ病の治療で使う気分安定薬の1つです。
躁症状やイライラの改善に特に効果を期待。再発予防の作用もあり継続使用が必要です。
副作用や過量時の影響を防ぐために「血中濃度」を定期的に測定することが望まれます。
もくじ
- (1)はじめに:気分安定薬バルプロ酸(デパケン)
- (2)バルプロ酸とは・適応病名・剤型
- (3)躁うつ病・気分安定薬と、バルプロ酸の症状への効果
- (4)バルプロ酸の立ち位置・弱点・長所・検討の場面
- (5)バルプロ酸の副作用と血中濃度
- (6)ラモトリギンとの併用には注意
- (7)バルプロ酸と妊娠
- (8)実際のバルプロ酸(デパケン)の使い方
- (9)まとめ
(1)はじめに:気分安定薬バルプロ酸(デパケン)
心療内科・精神科の薬。今回は「バルプロ酸(デパケン)についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
この心療内科・精神科の薬の動画では、メンタルヘルス分野の様々なお薬についてご紹介をしています。
今回は躁うつ病(双極性障害)で使われることの多い気分安定薬「バルプロ酸(デパケン)」について見ていきたいと思います。
(2)バルプロ酸とは・適応病名・剤型
<バルプロ酸とは>
まず、「バルプロ酸(デパケン)とは」ということですけれども、躁うつ病の代表的な薬・気分安定薬のひとつになります。
躁状態やイライラへの早目の効果が見込める薬ですけれども、一方でうつへの効果は弱めなことと、安全を図るため、血中濃度・薬の濃さを測る必要がある薬になります。
<バルプロ酸の適応病名と剤型>
このバルプロ酸の病名の適応なんですけれども、今回扱う「躁うつ病」以外に、「てんかん」に対しての抗てんかん薬として使うことがあるのと、「片頭痛」に対して片頭痛発作を抑える・抑制のために使うことがあります。
薬の剤型に関しては、一般的なデパケンというものと、ゆっくり効くタイプの徐放剤・デパケンRというものがあります。
実際、臨床ではこの徐放剤(デパケンR)の方を使うことが多いですので、それを念頭に今日は話をします。
(3)躁うつ病・気分安定薬と、バルプロ酸の症状への効果
<躁うつ病とは>
躁うつ病とはということですけれども、これはうつ症状とその逆の躁症状を周期的に繰り返す脳の不調です。
うつ病とは違う脳の不調のメカニズムが言われています。
治療としては、主に気分安定薬という薬を使って、安定と再燃予防を図っていきます。
<気分安定薬とは>
では、気分安定薬とはですけれども、これは躁うつ病の気分の波をなだらかにする薬になります。
躁の改善・うつの改善・再発予防、このすべてに効果を見込むものになります。
そして、再発予防という観点から安定している時でも続ける・継続することが必要になってきます。
<バルプロ酸の効果>
この中でバルプロ酸の効果ですけれども、まず躁の改善に関しては早目に十分な効果が期待できます。
特にイライラを伴うものに対しては、効果を期待します。
一方、うつの改善に関しては、効果は限定的と言われています。
再発予防・ぶり返しの予防に関しては効果を見込むんですけれども、別の薬リチウムが第1選択とされることが多いです。
(4)バルプロ酸の立ち位置・弱点・長所・検討の場面
気分安定薬の中でのバルプロ酸の立ち位置ですけど、「臨床的には使いやすい薬」ということになります。
<バルプロ酸の弱点>
バルプロ酸はまず弱点ですけれども、躁状態以外へのエビデンスのレベルは比較的弱いとされます。
特にうつに対しての効果は、限定的というのが臨床的にもあります。
そして、副作用は比較的あるのと、妊娠のした時のリスクもあるというところが弱点です。
<バルプロ酸の長所>
一方、バルプロ酸の長所ですけれども、「臨床で困る不調」に対して効果を見込みます。
例えば、躁状態であったり、イライラを伴うものであったり、急速交代型・躁とうつが頻繁に変わるものであったりに、効果が見込めます。
2つ目は、中断につながるような急性の副作用は少ない。
急な薬疹が出たり、急に手の震えが強く出たりなどでやめてしまう必要が出てくるということは少ないということがあります。
1日一回でよくて、リチウムと比べると安全に使いやすいというのが臨床的な印象です。
<検討する場面>
バルプロ酸を使うことを検討する場面ですけれども、まずは不機嫌やイライラが目立つタイプの躁にはよく使うことがあります。
2つ目としては、急速交代型・躁とうつを頻繁に交代するもの、および「混合状態」といって躁とうつが両方混じったようなタイプ。これにはバルプロ酸を使うことが多いです。
後はてんかんの既往がある方。これに関してはリチウムを使えないことがありますので、バルプロ酸をよく使います。
(5)バルプロ酸の副作用と血中濃度
<バルプロ酸の副作用>
1つ目は肝障害、肝臓に負担がかかることが指摘されます。
2つ目は、眠気やだるさ、特に量が多くなると出やすいです。
3つ目は人によるんですけれども、脱毛・毛が抜けやすくなるということがでる人がいます。
<血中濃度>
バルプロ酸は、血中濃度に注意というところがあります。
少な過ぎるとあまり効かない、多すぎると副作用ということですけど、主に数値で50から100という濃度が有効とされます。
100を超えてくると、副作用のリスクはちょっと高くなってきます。
<過量の時の影響>
どういうものが具体的に(濃度が)オーバーすると出るかと言いますと、1つ目は強い肝障害。肝臓に強い負担がかかってしまって影響が出る。
2つ目は意識障害・意識がもうろうとしたりすることがある。
背景としては、「高アンモニア血症」といって体の中のアンモニアが増えることが言われます。
<対策は血中濃度測定>
対策としては「血中濃度の測定」になります。
安定した後も、数ヶ月に一回測定してオーバーしていないかを確認するということは推奨されます。
特に濃度が高い状態で維持している方は、2から4カ月など頻繁に取ることをお勧めします。
(6)ラモトリギンとの併用には注意
注意としては、「ラモトリギン」という別の気分安定薬との併用についてであります。
これは同じ目的で使いまして、バルプロ酸は躁に対して効いて、ラモトリギンはうつに対して効くので、一緒に使うことは理論上はあり得ます。
しかし一方で「相互作用」といって一緒に使うと、薬の濃さが高くなりすぎてしまうことが多くありまして、副作用が強く出るリスクがあります。
なので、仮に使う場合も少ない量で慎重に使う必要があることがあります。
そのため、これは主治医の先生と相談をして慎重に相談をしていただけたらと思います。
(7)バルプロ酸と妊娠
バルプロ酸と妊娠ということですけども、妊娠した時にこのバルプロ酸、どうしてもお子さんへの「先天性奇形」などのリスクの指摘がありまして、影響は他の薬と比べて大きいところがあります。
ただし、急にやめてしまうと躁うつ病の症状が悪くなるリスクが高くありまして、これは主治医の先生と可能ならば、事前に相談していただけるとと思います。
候補としては、抗精神病薬など比較的リスクの少ない薬を使うというのがありますけれども、効果の相性がありますので、慎重に置き換えを主治医の先生と検討していただけたらと思います。
(8)実際のバルプロ酸(デパケン)の使い方
では、実際のバルプロ酸の使い方というのを見ていきます。
<開始と血中濃度測定>
まずは1日200から400ミリ、1日原則一回で始めていきます。
眠気やだるさなどが出ることがありますが、これは程度によって判断をしていきます。
そして、早い段階で血中濃度と肝機能を見ていきまして、適正に使えているかを見ていきます。
<調整と血中濃度測定>
その上で、効果や副作用・濃度から量を調整していきます。
数カ月ごとに血中濃度や肝機能を調べまして、必要に応じて量を調整していきます。
いわゆる急性期のような不安定な時は、濃度は高めに設定する・80-100くらいを設定して、安定ならば低め50とかもしくはそれより少なくという風に設定をしていきます。
<無効・不十分時>
躁が強い時に関しては、抗精神病薬を一緒に使うということを検討します。
逆にうつが続く場合は、抗うつ作用・うつを上げる作用のある抗精神病薬の併用を主に検討していきます。
波がある・不安定な時に関しては、リチウムを一緒に使うなど、他の方法を検討していきます。
<安定後・妊娠時・中毒疑い時>
そして、安定した後も再発予防という点からいわゆる維持量を保っていきます。
妊娠をした時に関しては、効果と量などを踏まえて主治医の先生とどうするか、薬を変えるかなど相談をしていきます。
そして、もうろうとするなど、過量・飲み過ぎてしまったなどの疑いがあった場合は、速やかに身体科・からだの科を受診してください。
(9)まとめ
今回はバルプロ酸(デパケン)について見てきました。
このバルプロ酸(デパケン)は躁うつ病で使う気分安定薬になりまして、特に躁・イライラを強いタイプの躁に対して効果を期待するものになります。
臨床的には使い易い薬とも言えます。ただ、時に肝臓のダメージ・肝障害などがありまして、定期的に採血をして、血中濃度・薬の濃さや肝機能などを見ていくことが望まれます。
効果不十分の時は、他の薬との併用も検討していきます。そして、妊娠がある場合は、対応を主治医とご相談いただけたらと思います。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)