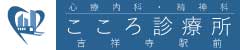家族が気づくうつ病・適応障害のサイン5つ
話さない、月曜朝の不調など
うつ病・適応障害になると家でも話さなくなるなど様々な変化が出ます。
これらの変化は時に早期発見・早期対策のヒントにもなります。
もくじ
- (1)はじめに
- (2)家で症状が目立つこともある
- (3)家族が気付くうつ病・適応障害のサイン5つ
- ①休日ぐったりしている
- ②イライラしやすい
- ③話さなくなる
- ④顔つきの変化
- ⑤月曜朝の不調
- (4)もし不調のサインがあったら
- (5)まとめ
(1)はじめに
うつ病適応障害セルフチェック。今回は「家族が気づくうつ病・適応障害のサイン5つ」についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
うつ病・適応障害は早期発見・早期対策が大事になります。
一方で自覚症状がわかりにくい場合、職場でも症状が見えにくい場合もあります。
むしろ、家で症状のサインが目立つということも少なくはありません。
では、家ではどんなうつ病・適応障害のサインが目立つでしょうか。
今回は「家族が気づくうつ病・適応障害のサイン5つ」について見ていきたいと思います。
(2)家で症状が目立つこともある
「家でこそ見える本音の状態」が大事です。
<うつ病とは>
うつ病は、落ち込みなど「うつ症状」が目立つ脳の不調になります。
脳のセロトニンの減少などが背景とされます。
うつ病ですと、「休日で家でもうつ症状が続きやすい」のが特徴です。
<適応障害とは>
適応障害は、ストレス反応での各種のうつ症状になります。
脳の不調はないとされ、ストレスから離れると原則改善するとされます。
休日は基本的には改善が見込まれますが、「仕事前の夜から朝に不調が出る」ことが多いです。
<典型的な家での休日の様子>
うつ病だと「休日も家でぐったりしている」ことが多いです。
適応障害だと基本的には休日は症状が目立たないですが、仕事のことを考えて落ち込むことがあります。
そして、仕事前日朝夜から月曜朝になると、うつ病・適応障害双方で不調が目立ちます。
<うつ病・適応障害の気づき方>
まずは「自覚症状」。自分で症状があって気付く場合があります。
また、「職場での様子の変化」で気づかれる場合があります。
もう一つあるのが「家での様子」になります。
一方、「自覚症状や職場の様子では不明な場合もある」ことがポイントです。
<自覚症状でわからない時>
まずは症状がゆっくり進むなどがあると、なかなか「気づかない」ことが少なくないです。
そしてもう一つは「症状を認めない」症状を疑っても、葛藤が強くあって認めないことはありえます。
そして、仮に症状があったとしても、それを「外にはなるべく見せない」場合もあります。
<職場では分からない時>
まずは「過剰適応」、仕事の場では適応しているように無理をして外には見えない一方、家で症状が強く出る方がいます。
また「外には隠す」という場合があり、その場合は外には目立たないことなります。
また、「他者とあんまり関わらない業種」の場合は、気づかれにくくなります。
これらの場合においては、「家での様子がヒント」になります。
(3)家族が気付くうつ病・適応障害のサイン5つ
「フラットな状態で見える症状」がポイントです。
①休日ぐったりしている
「以前と比べてもぐったりしている」というのがポイントです。
<休日ぐったりしている例>
まずは「休日ずっと寝ている」というところ。
2つ目としては「以前楽しめたようなことをしようとしなくなっている」というところ。
あとは日常生活で「何事もおっくうそうにしている」ことがあります。
<休日ぐったりの背景>
まずはうつ病などでの「意欲低下」が目立っている場合があります。
適応障害だと基本的には目立たない一方、「疲れ」の蓄積の場合もあります。
そして、家でも仕事のことを考えて「休めていない」時は特に注意が必要です。
②イライラしやすい
「以前とは、まるで人相が変わる」場合もあります。
<イライラしやすい例>
まずは「ささいなことで反応して怒る」場合。
あとは「家族に1種の八つ当たりをする」という場合。
そのほか「けんかが増える」こともあります。
<イライラしやすい背景>」
まずは「否定的思考」自己否定が周りへの否定にも繋がってきてイライラすることがあります。
また「易刺激性」、周囲に対して敏感になってしまう場合があります。
もう一つは「情動不安定」、感情のコントロールが取りにくくなっている場合があります。
③話さなくなる
「いつも話す人が黙るようになる」のがポイントです。
<話さなくなる例>
まずは「会話をあまりしなくなる」場合。
また「自分の部屋にこもって交流しなくなる」方がいます。
そして「独り言が目立つ」場合。
<話さなくなる背景>
まずは意欲や活力が低下する、うつ状態による症状。
後は「精神運動制止」といって活動全般が減る症状。
一方、人によっては「あえて話さない」場合もあります。
④顔つきの変化
「顔つきが変わって暗い雰囲気になる」場合があります。
<顔つきの変化の例>
まずは表情が減り「無表情になる」状態。
あとは「目がうつろになる」焦点が合いにくくなる場合。
あとは「肌荒れや無精ひげ」などセルフケア的な問題があります。
<顔つきの変化の背景>
まずは「落ち込み、抑うつ気分」が顔つきに反映されるという場合。
あとは「不眠」、眠れないためになかなか表情まで注意が行き届かなってしまう可能性。
そして「セルフケア困難」意欲などが低下して、日中のことがやりづらくなることがあります。
⑤月曜朝の不調
「仕事前になって不調が目立つ」というところ。
<月曜朝の不調の例>
まずは「月曜日朝あまり起きてこない」という場合。
また動きや表情に不調があり、聞いてみるとうつ症状がある場合。
また「体の症状がいろいろ出る」、頭痛、吐き気などが目立つ場合があります。
<月曜朝の不調の背景>
まず「仕事へのストレス反応」。「適応障害」の方は特にこの症状が多いです。
また、うつ病でも抑うつ気分が強まり、月曜朝の不調が出る事があります。
もう一つの背景は「不眠」、不眠からの不調もあり、仕事を考えての不眠もあります。
(4)もし不調のサインがあったら
「聞き手に回って、必要時は受診を勧める」方向です。
「家族の接し方の方向性」の要点は、「家を休める場にする」「聞き手になる」「必要時受診等を勧める」の3つです。
①家を休める場に
やはりうつの治療では休養が大事です。もし家でも休めないと、休める場がなく悪循環になってしまいます。
なので、家をゆったりできる場に何とかしていき、ご本人の休養を促していきます。
その中で、仮によかれであっても「否定的な感情をぶつける」「圧をかける」事は望ましくありません。
いわゆる「High-EE」と言われますが、これは非常に望ましくないとされます。
②聞き手になる
よかれと思っても、一方的な助言は圧力になり、逆効果になりやすいです。
なので、基本的にはそっと見守る方向ですが、相手から求めがあった場合に「聞き手」になれる準備をしておくのが大事です。
そして、それができる余力を保つために、「ご家族自身もセルフケア」をしっかりしておくことが大事です。
③必要時受診等を勧める
先程の「休む」「聞く」だけではなかなか改善しない場合も現実的には少なくありません。
その時に会社であれば、会社の「業務の相談」などを促してみるというのも一つ方法になります。
そして、不眠など実際に症状が強い場合は対策が必要のため、心療内科等の受診を勧める事になります。
(5)まとめ
今回はうつ病・適応障害セルフチェック「家族が気づくうつ病・適応障害のサイン5つ」を見てきました。
うつ病・適応障害では、家でも変化が出てくることが多くあります。早期発見のヒントにもなり、代表例は以下の5つです。
- ●休日ぐったりしている
- ●イライラしやすい
- ●話さなくなる
- ●顔つきの変化
- ●月曜朝の不調
接し方としては、まずは本人の休養を促しつつ、必要時「聞き手」になる対応をとっていただければと思います。
それでも困難な時は会社への相談や医療機関の受診を促していただけたらと思います。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)