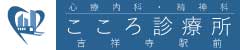更年期うつ
更年期に生じるうつ病・適応障害
更年期うつは、更年期にホルモン変化とストレスの双方を背景に発生するうつ病・適応障害です。
婦人科でのホルモン治療も検討しつつ、うつ病・適応障害の治療を並行していきます。
特に介護のストレスが大きくなる場合があり、その場合抱え込みすぎず介護制度の活用も検討します。
もくじ
(1)はじめに:更年期うつ
様々なうつ病・適応障害。今回は「更年期うつ」についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
心療内科において、いわゆる更年期でのうつ症状、このご相談というのはかなり多くあります。
一方で、1口に更年期うつといっても、その背景や対策というのはちょっと人によって変わってくる面がありますので、そこは見分けていくことが実際、臨床では大事になってきます。
そこも踏まえて、今回「更年期うつ」について見ていきたいと思います。
(2)更年期うつの概略と2つの背景
まず、「更年期うつ」まとめていきますと、主に閉経前後女性でいう閉経前後の数年間の間に生じるいろいろな落ち込みなどのうつ症状ということになってきます。
この「うつ症状」のほか、人によっては「体の症状」ホットフラッシュであったり、いろいろめまいであったり、そういったからだの症状が主に出る方も少なくはありません。
この「更年期うつ」の背景としては大きく言うと2つあります。1つ目が女性ホルモンの変化、ホルモンの変化。2つ目が年代によるストレスということになってきます。
①ホルモン変化
女性閉経前後の女性ホルモン、エストロゲンが変動しつつ減っていきます。
これによって体が慣れないということによって、さまざまな症状、体の症状が出るほか、うつや不安など精神的な症状、うつ症状も出ることがあります。
そして、これはかなり個人差が大きい、時期も個人差が大きいですし、程度も個人差が大きいということになります。
②年代のストレス
50歳前後。この更年期は体の変化、あと役割の変化というところがあります。そして、年齢的に今後への不安、主に老化・老後への不安ということが出てくる時期でもあります。
そして、人によってはもっと具体的な話として、介護・親御さんなどの介護の面のストレスが出ることが多い時期でもあります。
この2つは重なることは少なくありません。
(3)更年期うつの3つの治療
この更年期うつの治療ですけれども、大きく言うと3つです。1つ目はホルモン補充療法。これは婦人科の領域ですけどホルモン補充療法、2つ目が抗うつ薬や漢方薬、3つ目がストレス対策ということになります。
①ホルモン補充療法(HRT:詳細は婦人科にてご相談を)
大まかな内容を見ていきますと、これは女性ホルモン、エストロゲンなどを補充するという治療になります。補充方法などはちょっといろいろあります。
で、これは欧米だと非常に普及率が高くて3割ほどとも言われますけれども、日本ですと約2%、数字前後しますけれども、約2%と普及率が低いとされています。
これは一方で日本でも広まりつつあるんですけれども、一部血栓ができやすいなど、ちょっとこの治療ができないという方もいらっしゃるので、婦人科でしっかり相談してしっかり調べた上で導入を検討いただけたらと思います。
②抗うつ薬・漢方薬
基本的には、ホルモン補充療法以外に関しては、うつ病・適応障害に準じたメンタル面の治療をしていくということになります。
その上で、うつ・不安症状に対して抗うつ薬を使うことは検討されるところになります。
そして、よりマイルドな治療としての漢方薬が検討されることがあります。
これは身体の症状に使うこともありますし、精神面にも使うということが想定されます。
いくつか種類があって強み・弱みがありますので、これはご相談いただけたらというふうに思います。
③ストレス対策
ストレスが症状悪化に影響しますので、なるべくストレスを減らす環境の調整を図っていくのが大事になってきます。
特にその中でも介護ということに関しては、非常に長く続き、かつストレスになることがあります。
これはもう抱えすぎてしまうと、特にストレスになりますので、必要があれば介護保険制度を活用するということを検討いただけたらと思います。
もう一つとしては、ストレスの対処法・ストレスマネジメントの見直しというのも有効な場合があります。
(4)まとめ
今回は「更年期うつ」について見てまいりました。
更年期うつは主に閉経前後数年、45歳から55歳が一つ目安になります。こういった閉経前後に起こるさまざまなうつ症状であったり、体の症状だったりになります。
背景にはホルモンの変化ということが一つ。そしてもう一つがその年代によるストレスということがあります。
治療としては、婦人科でホルモン補充などをするかを検討しつつも、うつ病・適応障害に準じた治療・対策をとっていくということになります。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)