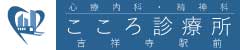適応障害と発達障害
発達障害背景に適応障害反復の時も
適応障害を繰り返す時、背景にASDやADHDといった「発達障害」が隠れている場合があります。
その場合診断を受ける事で取組みやADHDでは薬の治療、困難時は福祉制度活用の対策が取れる事があります。
適応障害反復時は、今と幼少期の症状を振り返り、該当なら受診・検査を経て診断に至ることが選択肢です。
もくじ
- (1)はじめに:「適応障害と発達障害」適応障害繰り返す時の背景
- (2)適応障害と、それを反復する場合
- (3)発達障害(ASD、ADHD)と二次障害での適応障害について
- (4)もし発達障害の診断あれば、対策はある
- (5)発達障害の診断を受けるには、その4段階
- (6)まとめ
(1)はじめに:「適応障害と発達障害」適応障害繰り返す時の背景
今回は「適応障害と発達障害」ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
人によっては、適応障害を何回も繰り返すという方がいます。
色々原因はありますが、人によっては背景に、自閉症スペクトラム(ASD)やADHDといった発達障害があります。その場合は、その発達障害を見つけて対応することが大事です。
今回は、「適応障害と発達障害」の話をやっていきたいと思います。
(2)適応障害と、それを反復する場合
<適応障害について>
適応障害は、ストレスからうつ症状などの様々なな症状が出てくる心の不調です。
ストレスへの対策が治療の柱になってきます。その中で、環境調整も大事になってきます。
一方で、人によっては環境調整を繰り返し行っても再発を繰り返してしまう方がいます。
<環境調整をしても適応障害を繰り返す背景>
想定の1つ目としてはご本人と環境のミスマッチが繰り返されてしまう場合
2つ目としては、自分を追い詰めたり、ストレスがたまりやすい「考え等のくせ」がある場合。
そして3つ目の原因としてが「背景に発達障害がある場合」です。
(3)発達障害(ASD、ADHD)と二次障害での適応障害について
<発達障害とは>
発達障害は、生まれながらの発達の強い偏りになります。代表的なのが自閉症スペクトラムASDとADHDです。
特性自体は取り組みで改善は見込める一方で、基本的には続いていきます。
そして、特性から社会や環境への不適応を繰り返し、うつ症状などの2次障害を繰り返すことがあります。
<ADHDとは>
ADHDは不注意・多動・衝動が特徴の発達障害です。
幼少期だと衝動を抑えられないところで見つかることが多いですが、大人になると、不注意等での仕事での不適応が多く見られます。
そして、不適応を繰り返すことで、適応障害を反復する場合があります。
<ASD(自閉症スペクトラム)とは>
ASDは「対人面(人間関係)のやりづらさ」と「こだわり」、この2つが特徴な発達障害です。
幼少期から人間関係がうまくいかなず孤立することがADHDと比べても多いですが、人によっては大人になってから分かることもあります。
同じく不適応から適応障害を繰り返すことがあります。
<発達障害に気づかない時の適応障害>
どうしても発達障害が一定水準以上あると、その特性から人や集団の中で適応しにくくなります。
そのため多くの集団の中でストレスが強くかかってしまい、結果「適応障害」にことがあります。
そうすると、仮に場所を変えても適応障害が繰り返されてしまいやすいことになります。
(4)もし発達障害の診断あれば、対策はある
<発達障害の診断つけば対応できる部分あり>
対応できる点の1つ目としては、仮にADHDの診断であれば改善を図る薬があること。
2つ目としては、仮に薬が合わなくても、特性に対して自ら勉強して対策を始めることが可能です。
3つ目としてはその特性があった上で、仕事などで「特性に合った環境」を探すことが可能になります。
<ADHDに合う仕事の例>
まずはあまりミスが致命傷にならないというところ。
あと変化への対応とか臨機応変な行動力が求められる物は得意なことが多いです。
そして、持久力よりは、その場の瞬発力がが求められる仕事は向いている場合が多いです。
<ASDに合う仕事>
まずは繰り返しと継続が大事になる仕事。
一方、対人関係の部分はそんなに多くない仕事。
そして繰り返し、ある種こだわってやり切ることが大事なことが、合っている場合が多いです。
<適応が難しい場合の対策>
どうしても適応困難な場合は福祉的なサポートを検討します。
1つ目としては「障害者枠」、発達障害を理解してもらいながら仕事を探すことが選択肢です。
2つ目としては「就労移行支援」最大2年リハビリで通いつつ、実習などもしつつ合う仕事を探していく方法です。
(5)発達障害の診断を受けるには、その4段階
このように、もし背景に発達障害があれば、それを知ることが大事という話をしましたが、ではどうやれば診断を受けられるでしょうか。
今回、これを4段階で見ていきたいと思います。1段階目は「発達障害の可能性を考える」、2段階目は「受診して相談をする」3段階目が「心理検査」、4段階目が「診断」になります。
①発達障害の可能性を考える
適応障害をなぜか繰り返してしまうという時に、発達障害はないかを検討します
その際、今や最近の症状、あと子供の頃の症状。この双方で発達障害の特性・症状がなかったかを振り返ります。
<ADHDの今の症状の例>
まずは仕事でミスや遅刻などが目立ってくること。
2つ目が課題を先送りにして間に合わずうまくいかないことが出てくる。
3つ目はつい言っててしまう「不用意な失言」が目立つというところ。これらが目安です。
<ADHDの子供の頃の症状の例>
まず多いのが、宿題などを先送りにして間に合わないこと。もしくは全部手伝ってもらったり、直前で一気にやる場合もあります。
2つ目としては、衝動的にかっとなりやすい、喧嘩になりやすいことです。これは大人になると改善することもあります。
3つ目は授業でよく眠くなる。特に興味のない授業でよく眠くなることがあります。
<ASDの今の症状の例>
1つ目としては対人面がなぜかなかなかうまくいかない。
2つ目が細かいことにこだわりすぎて全体が見えないと言われる。
3つ目が場の空気が読めず、浮いてしまったりすることがあります。
<ASDの子供の頃の症状の例>
1つ目は、なかなかなぜか友人ができず孤立してしまいやすいこと。「なぜかいじめに遭う」ことが背景の事もあります。
2つ目としては、独特なことに細かくこだわってしまう傾向がある。
3つ目が、「頑固」であったり、「予想外の時に混乱する」ということがありえます。
②受診して相談する
症状等で可能性を考えた上で、2段階目として「受診で相談をする」ことになります。
発達障害を扱っている心療内科、精神科を初診という形で受診をします。もし「うつ」など別のことで受診されていたら、そこで相談するのもいいと思います。
受診の際は様々内容の問診がありますが、主には今の症状と子供の頃の症状。ここの2つが主になると思われます。
その中で、通知票など「過去の状態が客観的にわかるもの」があると助かります。ただ、大人の方だとないこともあるので、絶対ではないと思われます。
③心理検査(主にWAIS検査)での心理検査
正式な診断においては、問診の状態を背景に、心理検査で客観的な情報を把握し、診断することが多いです。
どうしても「症状」は主観的な面があり、「客観的にどうか」を、枠組みが決まった心理検査で見ることで診断精度が上がるため、基本的には行うことが望まれます。
なお心理検査では、発達障害の傾向の側面のほか、得意・苦手分野と得意・苦手のばらつき、例えば聞くのが苦手で視覚優位であるなど、今後に生かせる他のヒントも出てくることがあります。
一方で費用や、「IQがわかってしまう心理的負担」は否定できないため、メリット・デメリット双方を踏まえた上で検査するか総合的に検討します。
④診断
典型的には、2段階目の問診と3段階目の心理検査、主観的症状と客観的症状を照らし合わせて最終診断になります。
その中でクリアに診断がならない、いわゆる「グレーゾーン」の場合もありますし、ASDとADHD合併の場合もあります。
その中で、もしADHDが(合併の場合も含めて)ある場合は、ADHD治療薬を使うか、薬の特性や利点・副作用等から総合的に検討します。
(6)まとめ
今回は、「適応障害と発達障害」ということで見てきました。
適応障害を繰り返す時に背景に「ASD・ADHD」といった発達障害がある場合があります。
この場合は、診断を受けることで対策が可能になり、困難な場合も福祉のサポートが選択肢になるため、有効性が示唆されます。
具体的な診断の受け方としては、まず今と幼少期の症状等で可能性を考え、その後、受診・心理検査を経て最終的に診断を受けます。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)