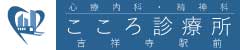うつ病の治し方5つ
抗うつ薬、休職等
うつ病は風邪のように短期では治らず薬の治療もしばしば必要です。
一方地道な取り組みの継続で、時に薬なしの治癒の余地があります。
もくじ
(1)はじめに
今回は「うつ病の治し方5つ」についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
気持ちの落ち込みが続く心の病気「うつ病」。心療内科・精神科の外来でも扱うことが多い病気です。
以前は「心の風邪」とも言われることもありましたが、実際は治療は時間がかかることも多いです。
しかし、必要な取り組みを一つずつ、地道に行っていけば、改善や治癒を目指していける余地がある病気でもあります。
今回は「うつ病の治し方5つ」を見ていきます。
(2)うつ病治療は総力戦
「さまざまな角度から取り組みを続ける」ことが大事です。
<うつ病とは>
うつ病は、落ち込みなどうつ症状が続く脳の不調になります。
脳のセロトニンの不足などが背景とされます。
休養・薬物療法・精神療法この3つが治療の柱とされます。
<うつ病は心の風邪か?>
「うつ病は心の風邪」は2000年前後疾患啓発のために使われたキャッチフレーズです。
これはうつ病啓発には大きな効果があったとも言われます。
一方で実態とは違うという批判もあります。
<風邪(アデノウィルス等感染症)の特徴>
風邪は基本的に比較的症状も軽くて、薬を使わなくてもよくなります。
かつ数日で自然によくなるのが一般的です。
<心の風邪?うつ病の特徴>
一方でうつ病は「社会生活に大きな影響がある」のが診断上の定義です。
そして基本的には「抗うつ薬など薬の治療が必要」です。
また「数カ月以上改善には要して再発のリスクもある」、実際風邪とはだいぶ違いがあります。
<薬なしでは限界がある>
うつ病は「脳の不調」、セロトニン不足などがあり、考え方などにも影響を与えます。
「休養」だけでは、改善までは非常に時間がかかってしまいます。
そして、うつが強い状態の場合「行動パターン」「考え方」などの振り返りは困難です。
<薬だけでも限界がある>
ストレスが強ければ、薬の効果は打ち消されてしまいます。
生活のリズムや行動パターンが崩れていれば、やはり薬の効果は打ち消されてしまいます。
そして「考えのくせ」で、自分で自分にストレスをかける状態でも、薬の効果は打ち消されます。
<治療の組み合わせと調整が大事>
うつ病では、薬と他のアプローチを合わせていくことが大事です。
そして病気の時期「病期」によって重点を置くところを変えていきます。
そして、自分の「くせ」を知って調整することが、特に再発予防に大事です。
(3)うつ病の治し方5つ
「さまざまな方法を組み合わせる」のがポイントです。
①早期発見・早期治療
「早目に気づいて早目に対策をとる」ことです。
<未治療期間>
未治療期間は、発症した後、治癒を開始するまでの期間です。
これが長ければ長いほど治療が苦戦してしまいます。
なので「早めの発見が大事」になります。
そして早目に気付くには、「自分の前触れを知る」ことが大事です。
<自分の前ぶれを知る>
うつ病の前ぶれは人により不眠・落ちこみなど様々です。
ただ同じ人ですと前触れは基本的に毎回同じです。
なので自分の「前ぶれ」は何かを知ることが大事です。
<前ぶれの例>
人によっては「不眠」眠れない症状。
人によっては「落ち込みが目立つ」方がいます。
また、人によっては頭痛など「体の症状」が目立つ方がいます。
<前触れに気づいたら>
まずは少し休養して改善を図ります。
そして、ストレスを減らすなどの対策をとりす。
それでも改善がなければ「受診」を検討します。
<受診を考える時の例>
まずは「対策をしても症状が続く時」。
続いては「悪化が続いてしまう時」。
そして「危険がある時(自分で自分をコントロールしにくい時)」になります。
②薬の治療
「うつ病の多くは薬物治療が必要」です。
<うつ病は「脳の不調」>
うつ病は、脳の「セロトニン」という物質の不足などが背景とされます。
「ストレスがなくなっても、すぐには改善しない」のが特徴です。
そして脳の不調から考え方など「脳の働き方」にも変化が出ます。
<主に抗うつ薬(SSRI等)を使う>
主に使う抗うつ薬「SSRI」は、脳のセロトニンを増やすことで改善を図る薬です。
これは改善のほか「再発予防」の意味でも効果を見込みます。
<SSRIの注意点>
1)すぐには効かない
効くまでに2から4週、時間差があります。
2)初期にお腹などの副作用
初期に吐き気、下痢など出る事があります。「体が慣れない」副作用のため、原則数日で改善します。
3)離脱症状
急に中断するとめまい等の「離脱症状」が出る事があります。
これは「依存」とは違い、ゆっくり減らすことで軽くすることが可能です。
<補助的に使う薬>
抗うつ薬は効くまで時間がかかるため、「待てない」場合に使うことがあります。
1)睡眠薬
「眠れない」からの悪循環を防ぐために使うことがあります。
2)抗不安薬
即効性がある不安を取る薬です不安から休めない等の悪循環を避けるため時に使いますが、「依存」には注意が必要です。
<抗うつ薬(SSRI等)中止時の注意点>
抗うつ薬は治癒すれば多くの場合中止可能ですが、主な注意点が2つあります。
1)長めに使う
改善後早めに減らしてしまうと再発のリスクが高いため、長めに使います。
2)ゆっくり減らす
急に減らすと離脱症状が出るため、ゆっくり減らすことでリスクを減らします。
③休養
「頭を休ませることが治療の土台」です。
<休養による治療>
休養では、文字通り休むことで徐々に改善を図っていきます。
「頭を休ませる」ことが大事なので、「考え事をなるべく避ける」のが非常に重要です。
そして効果の点からは、「休職」をするなど休養に専念することが本来は望まれます。
<休職による治療>
これは一旦仕事を休職して、治療に専念して改善を図る方法になります。
悪化を防ぐとともに、集中的に改善を見込む方法です。
期間は個人差ありますが「3か月」が目安です。
<休養さえすれば復帰できるか?
ここで「しっかり休みさえすれば復帰できますか」という質問があります。
回答は「休養だけでは復帰するにはリスクがある」になります。
<休職の3段階>
休職には以下の3段階があり、段階により療養・リハビリの重点を変えていきます。
1)前期(休養期)
この時期は何よりも休養に専念します。
2)中期(リハビリ期)
この時期は主に「体を動かすリハビリ」をして、活動量の回復を図ります。
3)後期は(復帰準備期)
ここでは「頭を使うリハビリ」をしつつ、実際の復職相談などをします。
<休職をしない場合>
一方、休職しない場合でも休日などできる限りの休養を確保することがやはり大事です。
その中で、短時間でも「効率的に休める方法」を探すことが大事です。
人によっては、体を動かしつつ頭を休める「アクティブレスト」が有効な場合もあります。
④ストレスマネジメント
ストレス対策は、再発予防にも大事です。
<ストレスとうつ病の関係>
ストレスはうつ病の発症原因になります。
そしてうつ病の悪化要因にもなります。
またストレスはうつ病の「再発」ぶり返す要因にもなります。
<ストレスを図で見ると:浴槽モデル>
ストレスと人を、「浴槽」と「水」に例えると見えやすい部分があります。
浴槽があって「たまるストレス」水のようにたまるストレスがある。
そして「出す」発散するものがあります。
そして「出す」より「たまる」が強いといずれあふれ、うつに至ります。
そして、どこまでは持ちこたえられるかの「容量」があります。
<ストレスマネジメントの基本>
先ほどの浴槽と水に準じて考えると以下の3つになります。
まず「ストレスをためない」こと。
2つ目が「発散を増やす」こと。
そして「容量(耐性)を増やす」ことです。。
<「ためない」例>
まずは嫌なことを言われた時に「受け流す」こと。
そしてストレスがたまりにくい「環境を選ぶ」こと。
3つ目が「考え過ぎない」ことになります。
<「発散を増やす」例>
まずは「ストレスの発散」の徹底。
そして「休養を確保して疲れを取る」こと。
そして「自分を励ます声掛け(アファメーション)」です。
<「耐性を増やす」例>
まずは自分の状態をしっかり把握する「マインドフルネス」。
また「生活リズムの確保」で余力を作ること。
そして自分の「軸」を明確化してブレないようにすることです。
⑤考えや行動の調整
自分を追い詰める「考え」「行動」を減らすことです。
<認知行動療法>
考え・行動の調整のため「認知行動療法」がよく使われます。
これは「考え」や「行動」の調整により、うつの改善や再発予防などを図る治療法です。
自分を追い詰めてしまう「考えのくせ」「行動パターン」を減らしていきます。
そしてプラスになる「考え方」「行動」を増やしていきます。
<考えの調整(認知再構成)>
認知再構成では、自分を追い詰める考えのくせを減らしていき、ストレスを減らします。
具体的にまずは自分の考えの「くせ」を観察して見つけていきます。
それに対して「別の見方(視点)」がないかを習慣的に繰り返し探しています。
<行動の調整(行動活性化)>
行動活性化では、自分に影響を与える「行動の質」を上げていきます。
具体的にはまず自分の「行動」と「その影響」を行動分析的に振り返っていきます。
もし良くない行動があれば、より良い行動パターンへ徐々に置き換える等で徐々に調整します。
(4)どこまで治るか?
「治癒」は見込める一方、「再発リスク」が残ります。
<「治る」の3段階とうつ病>
「治る」を表す言葉としては「寛解」「治癒」「完治」の3つがあります。
①寛解
これは「薬を使う中で」症状がなくなること。うつ病では達成可能です。
②治癒
薬なしでも症状がないことが数か月以上続くこと。これもうつ病では多くは達成可能です。
③完治
治癒(薬なしの安定)してかつ「再発リスクも少ない」ことです。
うつ病ではこの完治は「再発リスク」が残るため困難です。
<再発を防ぐ対策>
まずは「日頃のストレスや疲労対策」を続け予防すること。
2つ目は「ストレスや負荷を重ねない」ことでの予防。
3つ目は「もし前触れがあれば早めに対策を取る」。1日休む等で改善を図ります。
<もし再発しても、初回より有利な点あり>
もし再発してしまっても、初回と比べると有利な点もあります。
まず「早めに気づいて早めに対策ができる」こと。
2つ目は「合う薬がすでにわかっている」、合う治療法が見えていること。
3つ目は「すでに治した経験がある」こと。とるべき対策、やめた方がいい対策が見えています。
(5)まとめ
今回は「うつ病の直し方5つ」を見てきました。
うつ病は影響が大きく、治療にしばしば長期を要しますが、地道に治療を組み合わせて改善を図る余地があります。
代表的な症状への対策・方法は、以下の5つです。
- ●早期発見・早期治療
- ●薬の治療
- ●休養
- ●ストレスマネジメント
- ●考えや行動の調整
実際、薬なしで安定の「治癒」にはしばしば至りますが、再発のリスクは残ります。
それを防ぐために、日々のストレス対策などの取り組みが大事になってきます。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)